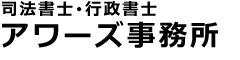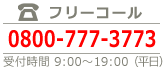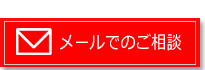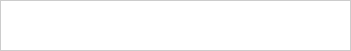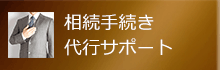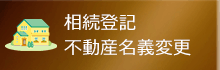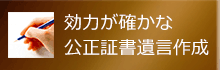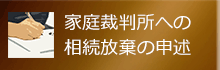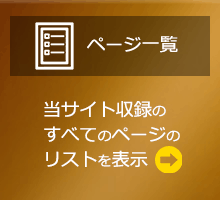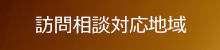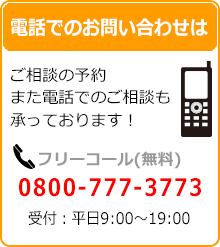相続人の調査・確定のための戸籍謄本などの収集、相続財産目録の作成ができたら、次は遺産分割協議です。
遺産分割協議書を作成するのには、
①相続人全員の合意内容を明確にして、後日の無用なトラブルをさける
②不動産、預貯金、株式、自動車などの名義変更手続きのため
③相続税の申告のため
といった、重要な目的があります。
遺産分割協議の話し合いがまとまったら、必ず遺産分割協議書を作成しておきましょう。
 土地・建物などの不動産の名義変更(相続登記)を司法書士に依頼した場合、作成してくれる遺産分割協議書は相続登記に必要な不動産についてしか記載されていないことが一般的です。
土地・建物などの不動産の名義変更(相続登記)を司法書士に依頼した場合、作成してくれる遺産分割協議書は相続登記に必要な不動産についてしか記載されていないことが一般的です。
そうすると、相続財産全般についての遺産分割協議書の作成は行政書士に依頼することになります。
遺産分割協議書は行政書士に、不動産の名義変更(相続登記)は司法書士に依頼するわけですが、なんか二度手間な感じですね。
アワーズ事務所は、司法書士、行政書士を兼営していますので、1つの窓口ですべての手続きを依頼していただくことができます。
司法書士・行政書士アワーズ事務所では、良質の法務サービスを適正な価格でご提供することを皆様にお約束いたします。
遺産分割協議書の作成サポート
▶遺産分割協議書の作成サポート
【サポート内容】
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の作成サポートの費用
遺産分割協議書の作成サポートの費用は、基本料金は税込20,000円の完全定額制です。
※協議書作成の資料となる相続人確定のための戸籍謄本などを、ご自分で収集している場合
総費用=基本料金(専門家報酬)20,000円(税込)
| 内容 | 費用 | 支払先 | |
|---|---|---|---|
| 初回相談 | 無料 | ||
| 専門家報酬 | 遺産分割協議書の作成サポート | 20,000円 | アワーズ事務所 |
遺産分割協議書が必要な理由
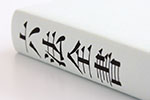 遺言書がないときは、相続の開始(被相続人の死亡)と同時に、故人(被相続人)の財産は相続人に承継されます。
遺言書がないときは、相続の開始(被相続人の死亡)と同時に、故人(被相続人)の財産は相続人に承継されます。
相続人となれる人の範囲や順位そして相続する割合は、民法で定められています。
相続人が2人以上いると、相続財産(遺産)は相続人全員が共有している状態(共同相続)になります。
この共有状態にある遺産を、それぞれの相続人のもの(単独財産)にするために遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは?
 被相続人の遺言書がない場合は、共同相続人全員で話し合って遺産の分割方法を決めます。
被相続人の遺言書がない場合は、共同相続人全員で話し合って遺産の分割方法を決めます。
分割協議は、相続人全員の参加と合意を必要としますので、相続人の一部が欠けていたり、一部の相続人の意思を無視して行ってしまうと、その話し合いは無効となってしまいます。
民法では、相続人に公平に遺産を配分するための割合(法定相続分)が定められています。
しかし、どんな場合でもこのルールに従って相続しなければならないわけではなく、相続人全員の合意によって、自由に相続分を決めることができます。
どの遺産を誰のものにするのかを、相続人全員で具体的に話し合って決めるのが遺産分割協議です。
遺産の分割の基準
 上記のように、相続する割合(相続分)には法定相続分という一定の基準がある一方、相続人全員の話し合いによって自由にその割合を決めることができます。
上記のように、相続する割合(相続分)には法定相続分という一定の基準がある一方、相続人全員の話し合いによって自由にその割合を決めることができます。
しかし、話し合いの場でそれぞれの相続人が自分の主張を譲らないとなると、紛争状態になってしまい最終的には裁判にも発展しかねません。
そこで、民法906条「遺産の分割の基準」をご紹介します。
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
【趣旨】
遺産分割においては、遺産に属する個別の物または権利の種類(土地、建物、現預金、その他)や、その遺産が持つ性質(換金性など)を念頭に置いて、どのように分割するのかを決める必要があります。
また、それぞれの相続人をとりまく一切の事情を考慮して分割しなければなりません。
配慮しなければならない各相続人の「年齢」とは、年少者への配慮、「心身の状態」としては、心身障害者への配慮、「生活の状況」としては、配偶者などが今まで居住してきた住居の確保が念頭に置かれています。
遺産分割の方法
遺産分割の方法としては、以下の3つがあります。
①現物分割
 「自宅の土地・建物は配偶者に、マンションは長男に、銀行預金は長女に」というように、個々の財産をそのまま各相続人に割り当てていく分割方法です。
「自宅の土地・建物は配偶者に、マンションは長男に、銀行預金は長女に」というように、個々の財産をそのまま各相続人に割り当てていく分割方法です。
現物分割は、手続きも簡単で、遺産をそのまま残せるメリットがありますが、遺産を公平に分けるのが難しい点がデメリットです。
②代償分割
 「長男が1人で土地・建物を取得する代わりに、長男が長女に対して500万円を支払う」というように、ある相続人が遺産を多く取得する代わりに、その代償をお金などで支払う方法です。
「長男が1人で土地・建物を取得する代わりに、長男が長女に対して500万円を支払う」というように、ある相続人が遺産を多く取得する代わりに、その代償をお金などで支払う方法です。
細分化するのが適当でない遺産、例えば自宅の土地・建物や被相続人が経営していた会社の株式などを、特定の相続人が取得する場合に適当な方法です。
しかし、特定の遺産を取得する相続人が、金銭などの代償物を支払えなければ実現できません。
③換価分割
 「相続した土地を売却して得た2000万円を、配偶者が1000万円、長男が500万円、長女が500万円を取得する」といように、遺産を売却してその代金を分配する方法です。
「相続した土地を売却して得た2000万円を、配偶者が1000万円、長男が500万円、長女が500万円を取得する」といように、遺産を売却してその代金を分配する方法です。
売却するためのてまと費用がかかることや、譲渡所得等の税金がかかる恐れがあります。
これらの点を専門家に相談するなどしたうえで、換価分割をするかどうかを検討してください。
これらの、3つの方法を上手に組み合わせて、遺産分割を行ってきます。
遺産分割協議書の書き方のポイント
①遺産分割協議書の形式や書式について、法令などで定められたルールはありません。
したがって、縦書き、横書きのどちらでもよく、ワープロなどで作成しても問題ありません。
②遺産分割協議書には、相続人全員が署名(または記名)し、印鑑登録済の実印で捺印する必要があります。
相続人の住所と氏名は、ワープロなどで作成して実印を押印すれば法的には有効ですが、後日のトラブルを避けるためには、相続人の住所と氏名は手書きにします。
また、住所は印鑑証明書のとおりに記載します。
③土地、建物などの不動産は、登記事項証明書をとりよせて正確に記載します。
この記載内容がまちがっていると、法務局での名義変更(相続登記)手続きを受け付けてもらえなくなります。
④預貯金、自動車、株式などは、できるだけ財産が特定できるように正確に記載します。
⑤現在判明していない遺産が発見された場合に、その遺産を誰が取得するのかを記載します。
この記載がないと、遺産分割協議成立のあとに発見された相続財産について、相続手続きをするために再度分割協議をしなければなりません。
⑥遺産分割協議書は相続人の数だけ作成して、相続人がそれぞれ1通ずつ保管します。
土地・建物などの不動産、預貯金、株式・債権などの有価証券、自動車などの相続人への名義変更をする場合には、その手続き上、遺産分割協議書が必要となるケースがあります。
これらの手続きは、重要な財産の名義を変更するという性質上、相当に厳重な手続きが要求されています。
書類の不備などによって、書類作成のやり直しや不足書類の収集などを求められ、再度出直しなどという無駄を省くためには、司法書士、行政書士などの専門家に依頼するのも、一つの方法です。
 司法書士・行政書士アワーズ事務所は、低廉で良質な法務サービスのご提供をモットーとしています。
司法書士・行政書士アワーズ事務所は、低廉で良質な法務サービスのご提供をモットーとしています。
遺産分割協議書の作成のみならず、遺言書の検認手続き、相続人の調査・確定のための戸籍謄本などの収集、相続財産目録の作成、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金、自動車の名義変更まで、相続手続き全般に特化した司法書士・行政書士事務所です。