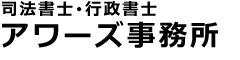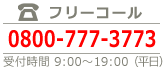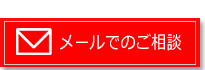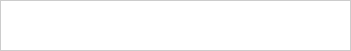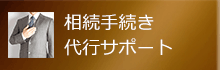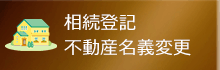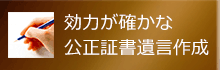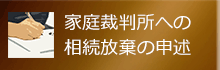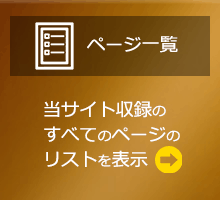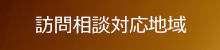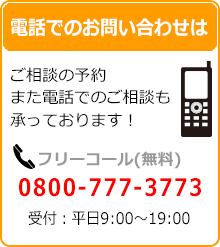相続放棄サポート
3か月を過ぎた相続放棄にも対応
初回は相談無料
出張相談、夜間や土日のご相談にも対応
※ご相談には事前予約が必要です。お気軽にお問合せ下さい。
フリーコール(平日8:30~19:00、土日9:00~17:00)
※スマートフォンでご覧の場合、下のボタンを押すと発信いただけます
※パソコンの場合はお手数ですが固定・携帯電話・スマートフォンから下記の番号を押してください
こんなことでお悩みではありませんか?
![]() 亡くなった兄の債権者から、突然電話がかかって来た。
亡くなった兄の債権者から、突然電話がかかって来た。
![]() 亡くなった夫あてに、債権回収会社から債務返済を督促する通知書が届いた。
亡くなった夫あてに、債権回収会社から債務返済を督促する通知書が届いた。
![]() 亡くなった父が、他人の連帯保証人となっていたことがわかった。
亡くなった父が、他人の連帯保証人となっていたことがわかった。
![]() 遺品を整理していたら、貸金業者のカードが見つかった。
遺品を整理していたら、貸金業者のカードが見つかった。
![]() 付き合いのない親戚から、遺産相続の件で連絡があった。
付き合いのない親戚から、遺産相続の件で連絡があった。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。(民法第896条)
これを包括継承といい、権利(プラスの財産)だけでなく義務(マイナスの財産)も引き継ぐことになります。
したがって、被相続人に借入金などの債務があった場合には、相続によってこれらのマイナス財産も引き継ぐことになります。
しかし、プラス財産に比べてマイナス財産が多い場合など、相続放棄によって相続の効果を拒否することができ、被相続人の債務を引き継ぐ必要がなくなります。
相続放棄のメリット
1. 借金等のマイナスの財産を相続せずに済む
 相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
その効果は絶対的であり、相続放棄した人へ被相続人の権利および義務はまったく移転しなかったこととなります。
その結果、被相続人の
・消費者金融やクレジット会社に対する借入金
・事業上の債務
・他の人の連帯保証人となったことによる債務
・未払家賃
・交通事故の損害賠償金
などのマイナスの財産を引き継ぐ必要がなくなります。
2. 相続トラブルに巻き込まれなくて済む
相続放棄することにより、
・遺産分割協議をめぐってのトラブル
・戸籍収集から始まる面倒な相続手続き
などから解放されます。
3. 特定の人に遺産を集中することができる
被相続人が会社を経営していた場合は、自社の株式を後継者に集中する必要が生じてきます。
また、会社の借入金を経営者が債務保証しているケースなど、経営にタッチしていない相続人が相続放棄をするメリットがでてきます。
このような場合に、後継者以外の相続人が相続放棄することにより、後継者に相続財産を集中することができます。
相続放棄のデメリット
1. 相続財産を一切相続できない
相続放棄をした人は、亡くなった方(被相続人)の相続財産の全てについて、相続することができなくなります。
マイナスの財産は相続したくないが、プラスの資産は相続したいという訳にはいきません。
相続放棄をする前には、しっかりとした相続財産の調査が必要です。
2. 相続放棄は撤回できない
相続放棄をした後から、被相続人にプラスの財産あったことがわかったとしても、相続放棄が家庭裁判所で受理された後は、これを撤回することができません。
相続放棄には、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」といいう期間の制限がありますが、その間にきちんと相続財産を調査する必要があります。
当事務所では、相続財産の調査などのサポートも行っています。
3. 新たな相続人が出てくる
相続放棄により、第一順位の相続人全員が相続放棄の申述をし、これが受理されると、第二順位の父母などの直系尊属が相続人となります。
第二順位相続人の全員が放棄をすると、次は兄弟姉妹などの第三順位相続人が相続人となります。
債務超過を理由に相続放棄をした場合は特に、次順位相続人へその旨の連絡をするなどの配慮が必要となります。
4. 連帯保証人への影響
被相続人に借金があるため、第三順位の相続人まで全員が相続放棄をしました。
これで一安心なのですが、被相続人の借金に連帯保証人がいた場合はどうなるのでしょうか?
相続放棄の効果は、あくまでも「被相続人」の債務を引き継がなくて済むということあり、連帯保証人の債務には及びません。
相続人の一人が連帯保証人である場合や、その他の連帯保証人への影響をしっかり検討したうえで、相続放棄をするのかどうかを決めなければなりません。
 「相続放棄サポート」では、次順位相続人や連帯保証人への影響などについてもしっかりご説明します。
「相続放棄サポート」では、次順位相続人や連帯保証人への影響などについてもしっかりご説明します。
相続放棄で失敗しないためのコツ
・相続財産の調査
・第三順位相続人までの調査や影響への配慮
・連帯保証人への影響など、
借入金などの債務を的確に把握したうえで、
・相続放棄申述書の作成
・戸籍謄本等の添付書類の収集
・上申書などの作成
を3か月という限定された期間内に行わなければなりません。
また、家庭裁判所に相続放棄申述の申立をして却下された場合、そのやり直しができないことも重要です。
さらに、相続放棄の申述が受理されたとしても、相続財産を隠匿しこれを消費した場合には、相続を単純承認したものとみなされます。
 したがって、相続放棄をするにあたっては、相続法に精通した専門家に依頼しアドバイスを受けた方が良いでしょう。
したがって、相続放棄をするにあたっては、相続法に精通した専門家に依頼しアドバイスを受けた方が良いでしょう。
「相続放棄サポート」を運営する司法書士・行政書士アワーズ事務所は、相続手続きを専門分野としており、これまでも数多くの相続案件を受託しており、ご依頼者から感謝の言葉を頂戴しています。
3か月経過後の相続放棄にも対応
1. 3か月の起算点は?
 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続放棄をしなければなりません。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続放棄をしなければなりません。
この3か月間がいわゆる「熟慮期間」です。
では、3か月の起算点となる「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、いつなのでしょうか?
それは、相続人が被相続人の死亡という事実を知り、その結果自分が相続人となったことを覚知した時とされています。
また、相続人が複数いる場合には、それぞれの相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から、個別に起算されます。
原則的には、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月を経過してしまうと、相続放棄をすることはできなくなります。
2. 3か月経過後の相続放棄は認められるのか?
それでは、熟慮期間の3か月が過ぎてしまうと、相続放棄は一切できなくなるのでしょうか?
実は、「被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があると認められるときには、相続放棄の起算点は、相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識することができる時とする。」という、有名な判例があります。
つまり、相続の開始を知ってから3か月が経過した後であっても、一定の要件を満すときには、その起算点が変わることになり、変更された起算点から3か月以内であれば相続放棄をすることができるという訳です。
3. 3か月経過後でも相続放棄が認められるケースとは?
・被相続人に相続財産が全くないと信じたこと
・そのように信じたことに相当な理由がること。
・相続人が相続財産の有無を調査することに著しく困難な事情があること。
上記の要件を満たす場合は、相続開始後3か月を経過した後でも相続放棄が可能となります。
相続の開始から3か月が経過していたとしても、ともかくあきらめずに専門家にご相談ください。
さてここで一つ注意が必要です。
それは、上記の要件を満たしても、変更されるのは熟慮期間の起算点だけだということです。
ですから、変更後の起算点から3か月が経過してしまうと、相続放棄はできないのです。
したがって、被相続人あてに債権者から借入金の督促状が届いたにもかかわらず、これを放置して3か月が経過してしまうと、相続放棄をすることは非常に難しくなります。
債権者からの督促状や訴状が届いた場合は、すぐにご相談ください。
 相続の開始から3か月を経過した後に、相続放棄の申述をする場合には、家庭裁判所に対して「上申書」を提出して、その事情や理由を説明しなければなりません。
相続の開始から3か月を経過した後に、相続放棄の申述をする場合には、家庭裁判所に対して「上申書」を提出して、その事情や理由を説明しなければなりません。
「相続放棄サポート」では、上申書の作成も含めてサポートしています。
相続放棄の流れ
1.相続放棄の相談

⑴被相続人の死亡日、それを知った日、申述人との関係(続柄など)
⑵相続財産(遺産)のプラス財産とマイナス財産(借金など)の把握状況
⑶これらの情報をお聴きしたうえで、相続放棄が可能なのか、相続放棄をすべきかどうかを検討します
![]()
2.費用のお見積もりと相続放棄サポートの申込

⑴報酬金額や実費の見込額をお伝えします。
⑵サポート内容や費用についてご納得いただけたら、相続放棄サポートをお申込みください。
申込は、電話相談あるいはメールのみでも受付ております。
![]()
3.戸籍などの必要書類の収集

⑴相続放棄の手続きには、被相続人の住民票の除票や死亡の記載のある戸籍など、申述書に添付する書類が必要となります。
⑵これらの必要書類は、ご依頼いただいた業務に基づいて、司法書士が職権により収集します。
![]()
4.申述書の作成と裁判所への提出

⑴「相続放棄申述書」は、ヒアリング内容や収集した戸籍等に基づいて当事務所で作成します。
⑵作成した申述書を申述人のご自宅に郵送しますので、ご署名・ご捺印のうえ当事務所にご返送ください。
⑶ご返送いただいた申述書は、必要書類を添えて当事務所から家庭裁判所に提出します。
![]()
5.家庭裁判所からの照会

⑴相続放棄申述書の提出から2週間ほどすると、家庭裁判所から申述人に「照会書」が届きます。
⑵照会書が届いたら、当事務所に照会書をメールまたはファックスでお送りください。
⑶当事務所で「照会書の回答の記入例」を作成し、ご提供します。
⑷記入例を基に照会書の回答を記入して、家庭裁判所にご返送ください。
![]()
6.相続放棄の受理

⑴照会書に対する回答を送って2週間ほどすると、家庭裁判所から相続放棄の申述を受理したとの通知書が届きます。
⑵届いた「相続放棄受理通知書」を当事務所にメールまたはファックスでお送りください。
⑶債権者や次順位相続人などに、当事務所から申述人の相続放棄が受理された旨を通知いたします
相続放棄サポートの費用
| 内容 | 費用 | |
|---|---|---|
| 初回相談 | 無料 | |
| 実費 | 相続放棄申述の申立 | 収入印紙800円 切手代470円 福岡家庭裁判所の場合) |
| 戸籍収集 | 戸籍 450円/通 除籍・原戸籍 750円/通 |
|
| 相続放棄サポートプラン | プランA (3ヶ月以内) |
プランB (3ヶ月経過後) |
|
|---|---|---|---|
| 報酬額 | 30,000円 | 50,000円 | |
| 項目 | サービス内容 | ||
| ヒアリング | 司法書士による相続放棄の状況に関するヒアリングを行います。 | 〇 | 〇 |
| 戸籍収集 | 相続放棄の手続に必要な戸籍謄本等を収集します。 | 〇 | 〇 |
| 申述書作成 | 相続放棄をするために必要な申述書の作成を行います。 | 〇 | 〇 |
| 書類提出 | 家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出します。 | 〇 | 〇 |
| 照会書への対応 | 家庭裁判所からの照会書に対する回答書の作成を支援します。 | 〇 | 〇 |
| 証明書の取寄せ | 必要に応じて家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書を取寄せます。 | 〇 | 〇 |
| 債権者通知 | 相続放棄が受理された旨を債権者へ通知します。 | 〇 | 〇 |
| 次順位相続通知 | 次順位相続人へ相続放棄した旨のを通知します。 | 〇 | 〇 |
| 2人目から割引 | 相続人2人以上が同時にご依頼される場合の割引 | 1人につき 5千円引 |
1人につき 1万円引 |
| 2件目から割引 | 1人の相続人が2件以上のご依頼をされる場合の割引 | - | 1人につき 1万円引 |
※上記の報酬金額は消費税抜きの価格です。
相続放棄に関するよくあるご質問
Q1 相続放棄は、誰がするのですか?
A1 相続放棄は、各相続人がすることになります。
相続の限定承認が、相続人全員でしなければならないのに対して、相続放棄は、相続人がそれぞれにすることができます。
Q2 未成年者や成年被後見人の場合は、どうすればいいですか?
A2 相続人が未成年者や成年被後見人であるときは、その法定代理人である親権者や成年後見人が代理して相続放棄の申述をすることになります。
未成年者とその法定代理人がいっしょに相続する場合で、未成年者のみが相続放棄をするときや、複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して相続放棄するときは、申述する未成年者について特別代理人の選任が必要となります。
Q3 相続放棄には、期間の制限がありますか?
A3 相続放棄の申述は、自己のために相続があったことを知ってから3か月以内にしなければなりません。
Q4 相続放棄の期限を延長することはできないのですか?
A4 相続人が、相続の開始を知って相続財産の調査をしたけれども、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られないときは、家庭裁判所に相続の承認または放棄の期間伸長の申立てができます。
Q5 相続が開始する前に、相続放棄できますか?
A5 相続の開始前に、あらかじめ相続の放棄をすることはできません。
Q6 相続の開始から3か月以上が経過しているのですが、相続放棄できますか?
A6 相続放棄の手続きは、相続人が被相続人が亡くなったことと、そのことによって自分が相続人になったこと事実を知ってから、3か月以内に申述しなければなりません。
ただし、相続財産が全くないと信じ、またそう信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部または一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。